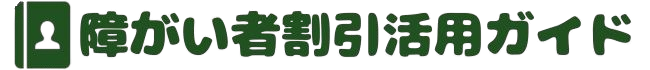「障がい者手帳って、名前は聞いたことあるけど、実際にはどんなもの?」
そんなふうに思っている人のために、この記事では障がい者手帳の種類やちがいを、やさしく説明します。
障がい者手帳には、3つの種類があります。
- 体に障がいがある人のための「身体障害者手帳」
- 知的な障がいがある人のための「療育手帳」
- 心や気持ちに関係する障がいに使える「精神障害者保健福祉手帳」
それぞれ使える人や、受けられるサポートが異なります。
「どの手帳が自分や家族に合っているのか」を考えるきっかけに、この記事を活用してみてください。
【結論】障がい者手帳は3種類!自分に合った手帳を選ぼう

障がい者手帳は、
- どんな種類があるか?
- 自分に合った手帳は?
を、知ることが大切です。
なぜなら手帳の種類によって、使えるサポートが違うからです。
合わない手帳を選ぶと、必要な助けが受けられないことも。
そこでまずは、それぞれの手帳についてわかりやすく説明していきます。
障がい者手帳の種類とちがいを簡単に説明
障がい者手帳には、3つの種類があります。
- 身体障害者手帳(からだに障がいがある人)
- 療育手帳(知的な障がいがある人)
- 精神障害者保健福祉手帳(こころの病気や障がいがある人)
それぞれ、どんな障がいの人が使えるかが違います。
たとえば「発達障がい」の人は、場合によっては「療育手帳」か「精神障害者手帳」のどちらか、または両方の対象になることがあります。
名前だけでは分かりにくいので、まずはそれぞれ詳しく紹介します。
手帳を使う目的で選ぼう
障がい者手帳は、生活を少しでも楽にするための制度です。
たとえば、
- 電車やバスを安く使いたい
- 働くときにサポートがほしい
- 病院の費用を安くしたい
このように、自分がどんな助けを必要としているかによって、合う手帳は変わってきます。
「どんなことで困っているのか」「どんな助けがあったらうれしいか」を考えてみましょう。
そうすれば、自分に合った手帳が見つかりやすくなります。
自分や家族に必要なサポートから考えよう
まずは、「どんな助けがあれば生活が楽になるか」を考えてみましょう。
- 通院が多いなら → 医療費のサポートがある手帳が便利
- 移動が大変なら → 電車やバスの割引がある手帳が役立つ
このように、生活の中で「何が一番つらいのか」「どんなサポートがほしいのか」から考えると、ぴったりの手帳を選ぶことができます。
等級ってなに?高いとサポートが手厚いけど自分では決められない
障がい者手帳には「等級(とうきゅう)」というものがあります。
これは、障がいの重さを表すランクのようなもので、数字が小さいほど(たとえば1級など)、重い障がいとされます。
等級が高い(=障がいの重さが大きい)ほど、もらえるサポートの内容も多くなるのも特徴です。
たとえば、税金の控除が大きくなったり、電車やバスが無料になったりすることもあります。
ただし、この等級は自分で決めることはできません。
等級は、お医者さんの診断や市役所の審査によって決まります。
「できるだけ高い等級がほしい」と思っても、実際の障がいの状態にあわせて決まるので、自分でえらぶことはできません。
大切なのは、正しい情報を伝えて、自分に合ったサポートを受けることです。
【違いを比較】障がい者手帳の3種類をわかりやすく紹介

障がい者手帳には、3つの種類があります。
それぞれ使える人やサポート内容がちがうので、しっかり知っておくことが大切です。
ここでは3つの手帳について、わかりやすく説明します。
身体障害者手帳とは?対象・等級・受けられる支援まとめ
身体障害者手帳は、体に障がいがある人が使える手帳です。
たとえば、目が見えにくい人、耳が聞こえにくい人、手足がうまく動かせない人、心臓や腎臓などの内臓に障がいがある人が対象です。
この手帳には「1級」から「6級」までのランク(等級)があり、数字が小さいほど重い障がいになります。
等級によって、使えるサポートも変わってきます。
たとえば、
- 電車やバスの料金が安くなる
- 税金が少なくなる
- 病院の費用を助けてもらえる
などのサポートがあります。
療育手帳とは?知的障がいとの関係や等級のしくみ
療育手帳は、知的な障がいがある人のための手帳です。
小さいころから発達がゆっくりだったり、日常生活に手助けが必要な人が対象になります。
等級は市や県によってちがいますが、よくあるのは「A(重い)」と「B(軽い〜中くらい)」に分ける方法です。
この手帳を持っていると、
- 支援施設を使える
- 税金が安くなる
- 電車やバスの割引がある などのサポートが受けられます。
精神障害者保健福祉手帳とは?対象になる症状とメリット
精神障害者保健福祉手帳は、心の病気や気持ちに関する障がいがある人のための手帳です。
うつ病、統合失調症、発達障がい、そううつ病などの人が対象です。
等級は「1級」から「3級」まであり、1級が一番重い障がいです。
この手帳を持っていると、
- 仕事のときにサポートを受けられる
- 病院代の助けが出る(地域による)
- 電車やバスの割引がある などのメリットがあります。
心の病気は外から見えにくいですが、手帳を持つことで必要な助けを受けやすくなります。
障害者手帳の種類について まとめ

障がい者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つがあります。
それぞれ、使える人やサポートの内容がちがいます。
また、「等級(とうきゅう)」というランクがあって、等級が高い(重い障がい)ほど、もらえるサポートも多くなります。
ただし、この等級は自分で決められず、お医者さんの診断や役所の判断で決まります。
大事なのは、「自分にどんなサポートが必要か」を考えること。
手帳を使うことで、病院に通うとき、仕事を探すとき、移動するときなど、生活のいろいろな場面で助けを受けられるようになります。
まずは、自分や家族がどんなことで困っているのかを考えて、それに合った手帳を選ぶところから始めてみましょう。